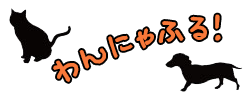愛犬がチョコレートを食べたときの対処法
犬を飼っている人のなかでは有名な犬に食べさせてはいけない食べ物『チョコレート』。
どんなに気をつけていても、留守中やちょっと目を放した隙に愛犬が食べちゃった!なんてことがあるかもしれません。
そんなとき、私たち飼い主があわてず冷静に対処することが愛犬の命を救う第一歩になります。
チョコレートを食べるとどんな症状が出るのか、どのくらい食べると危険なのか、犬のチョコレート中毒についてまとめてみました。
どんな症状が出る?
チョコレート中毒は、チョコレートの原材料であるカカオに含まれている“デオブロミン”という成分によって起こります。
“デオブロミン”はカカオの含有量が多いほど多く含まれているので、ミルクチョコレートよりもビターチョコレートや製菓用のチョコレートのほうが1gあたりの“デオブロミン”の量は多いです。
この“デオブロミン”が犬にとっては中枢神経を刺激する毒素となり、痙攣や発作、嘔吐、不整脈などを引き起こします。もちろん、大量に食べると死にいたることもあります。
どのくらい食べると危険?
では、どのくらいチョコレートを食べると犬にとって危険なのでしょうか?
“テオブロミン”の犬における致死量は、体重1kgあたり250~500mgといわれています。
これは、ミルクチョコレートで約560g、ビターチョコレートでは約60gにあたります。 もちろんチョコレートによって差はありますが、許容量は多いので、飼い主さんの食べていたチョコレートを一舐めした、大型犬が一欠けら食べたといった程度では症状が出ることは少ないようです。
食べちゃったらどうしたらいい?
食べた量がかなり少ないようならお家で少し様子をみてあげてもいいでしょう。
しかし、食べた量が多い場合はなるべくはやく動物病院を受診しましょう! 犬が食べたものを吐き戻させる催吐処置ができるのはそのものを食べて1~2時間以内が限界といわれています。
時間がたてばたつほど消化管から毒素が吸収されて吐かせるのが難しくなります。 動物病院では、チョコレートを食べてすぐであれば、オキシドールを水で薄めたものを飲ませたり、それでだめなら血管からお薬を注射して、まずは吐かせます。
そして、皮下点滴や静脈点滴をして身体の中の毒素を薄めて排出を促します。症状が出ている場合は血液検査や入院が必要になる場合もあるでしょう。
お家でオキシドールや食塩で吐かせる方法はインターネットでもよく紹介されていますが、どちらも食道や胃が荒れますので、その後に血を吐いたり、なかなか吐き気が治まらないことがあります。
お家で吐かせることに成功しても、動物病院を受診することをオススメします。

By: Tatsuo Yamashita
その他にも気をつけたいこと
チョコレートの危険性は有名ですが、他にもマカダミナナッツチョコレートのマカダミアナッツは犬の腎臓に有毒性がありますし、チョコレートケーキの生クリームやスポンジに含まれる脂肪分の摂り過ぎは膵炎のリスクが高まります。
人にとってはどちらもとっても美味しいものですが、犬にとっては危険ですのでチョコレートと併せて気をつけておきましょう!