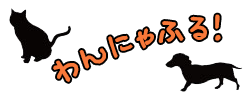飼い猫があまり水を飲まないけれど、大丈夫?
汗ばむ季節になり、熱中症対策を万全にしているおうちも多いのではないでしょうか。
そんな中で心配になるのが、飼い猫が飲む水の量。
なんだか少ない気がする…と感じる飼い主さんも多いのではないでしょうか。
今回はあまり水を飲まない猫が気を付けたい病気についてお教えますので、ぜひ参考にしてみてくださいね。
猫はあまり水を飲まないってホント?
猫の祖先のリビアヤマネコは砂漠に住んでいたので、あまり水を飲みませんでした。
イエネコもその名残りがあるので、猫はあまり水を飲まない生き物だといわれています。
しかし、あまりにも水を飲まないと濃いおしっこが出るようになってしまいます。
濃いおしっこは臭いがきついだけでなく、いろいろな病気を引きおこす原因にもなるので要注意です。
考えられる主な病気と対策法は?
尿路結石
特にオス猫がかかりやすいおしっこの病気といわれています。
去勢手術後のオス猫はとくに注意が必要な病気です。
尿路結石になると、腎臓から尿管、膀胱、尿道の中に結晶や結石ができてしまうので、それが膀胱や尿道を傷つけたり、尿道に詰まったりします。
石の大きさは個体差があり、大きいものだと数センチにもなります。
この病気は肥満の猫もかかる子が多いので、要注意です。
軽度の場合は、結石を溶かす薬や療法食を活用して治療していきます。
しかし重、症化した場合は、手術で取り除くこともあります。
また、結石が尿道に詰まっていておしっこが出にくくなっている場合は、尿道口からカテーテルを入れて尿道を洗浄することでスムーズに排尿できるようにします。
結石がとれない場合や何度も繰り返す場合は、ペニスを整形して尿道を短くする手術を行うこともあります。
予防としては、濃いおしっこをださないように水をたくさん飲ませることが1番オススメです。
また、食事管理もしっかりして、肥満を防ぐことも大切になってきます。
膀胱炎
排尿のときに激しい痛みを伴うのが、この病気です。
痛いので、トイレの中に入ると泣き叫ぶ姿がみられるようになります。
初期の症状としては多飲多尿がみられ、おしっこの色も濃くなり、臭いもきつくなります。
病気が進行すると血尿が見られたり、食欲不振や発熱といった症状がみられるようになります。
膀胱炎は細菌性のものだけでなく、ストレスによって引き起こされることもあります。
治療法としては、薬を投与しながら細菌をやっつけていきます。
再発したり、病気が長引く場合は他の疾患が原因となって引き起こされている可能性があるので、そちらの治療も行っていきます。
予防法としてはこちらもおしっこが濃くならないように水を飲ませることが大切になってきます。
また、ストレスをためない環境作りも必要になってきます。
水を飲ませる方法
水飲み場を多くする
水を摂取しやすいように水飲み場を増やすのもひとつの方法です。
特に夏場は水が早くなくなってしまいがちなので、多めに用意することが大切になってきます。
ウェットフードを与える
ウェットフードは水分を多く含んでいるので、水を飲んでくれない子には効果的です。
においが強いので猫が好んで食べてくれやすいのもポイントです。
しかし与えすぎると下痢になってしまう場合もあるので、ほどほどにしましょう。
シリンジで飲ませる
自力でどうしても飲んでくれない子にはシリンジで水を与えてあげるのもオススメです。
こうすれば確実に水分をとらせることができるので、飼い主さんも安心することができます。

By: liz west
まとめ
猫にとって水は大切なものです。
どれだけ飲んでいるか飼い主さんがしっかりとチェックしておくことが大切になってきます。
また、猫は繊細で神経質な性格の子が多いため、猫は犬よりも膀胱炎になりやすいともいわれています。
ストレスフリーな生活を送れるように飼い主さんがフォローしてあげるようにしましょうね。