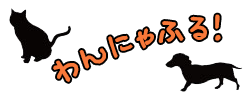水をよく飲む猫が注意したい病気まとめ
気温が暑くなってくると気になるのが、飼い猫の飲み水の量。
飼い猫が飲む水の量が最近増えてきたので不安…という飼い主さんも多いのではないでしょうか。
今回は水をよく飲む猫が注意したい病気についてお教えいたしますので、ぜひ参考にしてみてくださいね。
そもそも猫はたくさん水を飲む生き物なの?
猫はもともとはあまり水を飲まない動物です。
そのため、たくさん水を飲む場合は、体になんらかの病気が隠れている可能性があります。
いつもより排尿が多いと感じたら、多飲している可能性があるの注意しながら観察しましょう。
また、水分の標準摂取量は体重3kgで120~150ml、4kgで150~190ml、5kgで170~220mlとのことなので参考にしてみてくださいね。
考えられる主な病気と対策法
糖尿病
糖尿病の初期には、たくさん食べるのに体重が増えないといった症状や多飲多尿といった症状がみられます。
病気が進行すると神経系に影響がでて、しっかり歩けなくなったり、感染症にかかりやすくなったりします。
重度になると嘔吐や下痢を繰り返したり、食欲不振になり最悪の場合は死に至ることもあるので注意が必要です。
治療としてはインスリン注射を行いながら、ストレスなどを溜めない生活環境にしていくことが大切です。
また、あらかじめストレスを溜めさせない環境作りをしていると、糖尿病の予防になります。
もちろん人間のおやつをあげないようにして肥満を防ぐことも大切な予防策です。
糸球体腎炎
初期症状はほとんど無自覚で、飼い主さんも気づきにくいのがこの病気です。
尿検査をしてみると尿中タンパク質が増えている程度なのが特徴。
しかし、病気が進行すると、元気がなくなり、毛ヅヤも悪くなり、多飲多尿の症状が見られるようになります。
さらに重症化すると嘔吐や下痢、食欲不振といった症状もみられるようになり慢性腎不全の症状がみられるようになります。
この病気は他の病気が原因で引き起こされることがあるので、その場合はそちらの病気の治療をすることで治していきます。
原因が不明な場合は、免疫抑制剤や抗炎症剤などを使用しながら、食事にも気をつけて治療していきます。
この病気を起こすきっかけになる「猫エイズ」や「パルボ」などはワクチンをすることで防げるものなので、年に1回のワクチン接種が大切になってきます。
子宮蓄膿症
この病気はメス猫特有のものです。
子宮に細菌が感染することで炎症が起こり、子宮内に膿がたまります。
子宮頸管が開いているか閉じているかで、「開放性」と「閉塞性」に分けられるのも特徴です。
「開放性」は、膿が外陰部から排泄されるのでお尻や陰部、後ろ足に悪臭をともなった汚れがみられるようになり、食欲不振や多飲多尿と言った症状もみられます。
「閉塞性」では、膿や細菌の毒素が子宮内にたまるので、お腹が膨んだり、急性腎不全になったりとより重症化しやすいです。
この病気は抗生剤などで体を状態を安定させてから、子宮と卵巣を摘出するのが主な治療法ですが、あらかじめ避妊手術をしていればかからないという特徴もあります。
慢性腎不全
シニア猫が命を落とす原因になりやすいのが、この病気です。
初期症状としては多飲多尿だけがみられるので、病気に気づかないことも多いです。
しかし、病気が進行してくると食欲不振になったり、活発さがなくなったりします。
毛ヅヤも悪くなり、目に異常がでてくることもあります。
末期になると「尿毒症」になり、こん睡状態に陥ることもある恐ろしい病気です。
この病気は糸球体腎炎などが原因で引き起こされることが多いといわれています。
悪化させないためにも、いつもと少しでもおかしいと思ったらすぐに病院に連れていくようにしましょう。
また、予防策として、原因となるほかの病気から猫を守るためにワクチン接種をするのもオススメです。

By: frankieleon
まとめ
他にも多飲多尿が症状として現れる病気はいくつかあります。
どの病気にも共通していえることは、早めの治療が大切になってくるということです。
ただの水の飲みすぎだと油断しないで、尿の量もあきらかに多いと感じたら早めに病院に連れていくようにしましょう。
また、メンタル面でも無理や我慢をさせないように飼い主さんがスキンシップをとってあげることも心がけましょうね。